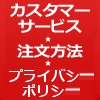Spending Money on AI Class, Worth It?
AI使いこなしに有料クラスは必要? + ディープ・シークは?
CUBE New Yorkさんのサイトを毎日のようにチェックしています。
最近「チャットGPTのようなAIを使いこなせないと、時代に取り残される」と言われるようになりましたが、
どう使ったら良いのかが分からずにいたところ、友達にオンラインの「チャットGPT使いこなし口座」のようなものを一緒に受けようと誘われました。
私はチャットGPTが気になっていたこともあって、「今後転職する際とかに使いこなせると有利かな?」と考えたのですが、
もう1人同席していた友達には「それって親の世代がインターネットのクラスを取って、マウスの使い方を習っていたような感じ?」と馬鹿にされてしまい、
果たしてAIはお金を払って学ぶべきものなのか、それともインターネットみたいに「気付いたら皆使っていた」となるものなのかと考えてしまいました。
アメリカでもAIを学ぶクラスなどが流行っているのでしょうか。そして秋山さんはどうお考えですか。
他愛のない質問で恥ずかしいかと思ったのですが、秋山さんなら先読みが深いかなと思ってメールしてしまいました。
よろしくお願いします。
ー E ー
この質問に尋ねるべきは…
アメリカは、チャットGPTがリリースされた途端に大学生は論文制作に、高校生は課題や宿題に利用し始め、若い世代を中心に クラスやレクチャー等が登場するまでも無く
あっという間に普及してしまいました。その際、使い方や応用についてはチャットGPT自体に尋ねて学ぶケースが多く、もちろん簡単なチュートリアルはYouTube上にアップされていました。
後に就職のレジュメ(履歴書)をチャットGPTに執筆させるケースが増えたようですが、簡単に見破られてしまうため、今ではレジュメ執筆にチャットGPTを使用すると、
その時点で採用チャンスを逃すと言われています。
クラスやレクチャーを受けるかについては、チャットGPTに尋ねてみるのが一番かと思います。でもチャットGPTは正攻法で尋ねると
本当に当たり前で客観的な回答しかしてくれませんので、ちょっと捻りとアングルを変えた質問を以下の通りに投げかけて見ました。
私:
チャットGPTを使いこなすための様々な有料レクチャーやクラスがありますが、それを受ける必要はありますか。
チャットGPT自体の方が、クラスの講師よりも確実に賢いと思うのですが、いかがでしょう?
ChatGPT:
確かに、ChatGPT自体が非常に強力なツールであるため、適切な使い方を試行錯誤するだけでも多くのことが可能になります。
有料のレクチャーやクラスを受けるべきかどうかは 以下に示す「何を学びたいか」によります。
- 基礎的な使い方:
基本的な使い方は自己学習でも十分習得できますし、ChatGPTに「この機能をどう使うの?」と尋ねることで答えを得ることができます。
例:「ChatGPTをExcelの関数作成にどう活用すればいいか教えて」と聞けば、その場で学べます。 - 高度なテクニックや応用スキル:
「業務プロセスへの導入方法」や「プログラミングと組み合わせた活用」といった専門的な応用は、有料クラスで具体的な事例や応用事例を効率よく学べる可能性があります。
ChatGPTの方が 講師より賢いかについては、確かにChatGPTは膨大な情報を瞬時に処理でき、専門的な質問にも対応できます。しかし、人間の講師には次のような強みがあります。
- 受講者の背景やレベルに応じた個人指導。(チャットボットで 個別ニーズに対応するには質問の工夫が必要です。)
- 特定の業界や実務経験を持つ講師は、実際のプロジェクトでの課題やその解決方法を具体的に共有してくれることがあります。
- 「何を学べば良いのか分からない」人であれば、講師が提示する学習内容で効率よく学べる可能性があります。
★ 結論 ★
あなたが以下の状況であれば、有料クラスに価値があるかもしれません。
- ChatGPTを使う具体的な目的があり、それに特化した知識や事例を効率よく学びたい。
- 忙しくて試行錯誤に時間をかけたくない。
- 特定の業界や業務における専門的な活用法を知りたい。
一方で、以下のような場合には不要かもしれません。
- 自分で調べたり、ChatGPTに直接質問して学ぶ意欲がある。
- 特定の目的が明確であり、それを少しずつ自力で試したい。
どちらを選んでも、ChatGPTそのものが学習の強力なツールであることは変わりませんので、「質問力」や「活用の工夫」を磨くことが最も重要です!
私のコメント:
オンライン上のクラスは、既にプログラムが一律でパッケージ化されているものが殆どですので、チャットGPTが列挙するクラスを取るメリットの一部は当てはまらないかと思います。
学習法や成果については「有益なクラスが選べるかで決まる」ことを、遠回しかつ、まどろっこしく伝えてくれているのがチャットGPTです。
さらに深く掘り下げて質問…

私:
チャットGPTの進化によって、クラスで学んだ知識が今後、不要になるケースもあるのでしょうか。
ChatGPT:
はい、その可能性は十分にあります。チャットGPTのようなAIツールは急速に進化しており、現在必要とされる知識やスキルが、やがては不要になることがあります。
以下に理由とそうなる場合の対策を挙げます。
★ AIの進化で クラスで学んだ知識が「不要」になる理由
- インターフェースの簡略化
AIはより直感的でユーザーフレンドリーなものへ進化していきます。 例えば、 現在は「良いプロンプト(ユーザによる指示や質問)の作り方」が重要ですが、将来的にAIが曖昧な指示を自動的に解釈・補完できるようになれば、複雑なプロンプト設計の知識は必要なくなるでしょう。 - 自動化の高度化
特定のタスクやワークフローを自動的に構築する能力が向上すれば、人間がプロセスを細かく設計する必要がなくなります。たとえば、AIが「データを収集し、分析し、報告書を作成する」といった一連の作業を完全に自動化するようになると、 手動でその流れを設定するスキルの価値は低下します。 - 知識の陳腐化
AIツールのアップデートや新機能の追加により、過去の使い方やコツが役立たなくなる場合があります。たとえば、過去のバージョンで必要だった細かいチューニングや設定が、新しいバージョンでは不要になることがあります。
★ クラスで学ぶ知識が不要になる場合への対策
- AIの進化により一部の知識が不要になっても、AIを適切に使うための論理的思考や特定課題の解決力、新しい機能やツールへの適応力は役立ちます。 有料クラスがこれらを重視しているなら学ぶ価値があります。
- 法律業務や医療分野でのAIの使い方、データ分析やプログラミングとの連携方法などは、AIの進化により詳細が変わることはあっても、基本的なフレームワークは役立つ可能性が高いです。
- 短期的視点では、学んだ知識で現在のタスクや課題を効率的に解決する助けになるはずです。 長期的視点では、技術の進化に応じて柔軟に学び続ける姿勢が重要です。
★ 結論 ★
AIの進化により、現在の知識が不要になる可能性はありますが、基礎的なスキルや応用力、適応力は長く役立ちますので、有料クラスがそれらを重視しているなら価値があります。そうでない場合は自己学習で十分対応可能です。
ポイントは、「AIの進化を恐れるのではなく、その変化に対応する力を磨くこと」です。
私のコメント:
またしても、当たり障りの無いオブラートに包むスタイルの回答だったので、
もうちょっと質問で仕掛けて見ました。
私:
頂いた回答は、クラスを運営するビジネスに配慮した、いわばデュプロマティックな回答に思えますが、実際にチャットGPTには、既存のビジネスへの配慮がプログラムされているのでしょうか。
AI進化は日進月歩ですが、チャットGPTについて教えるクラスは、どのくらいの頻度でそのカリキュラムをアップデートする必要があると思われますか。
ChatGPT:
ご質問、非常に鋭い視点ですね!2つのご質問にお答えします。
1. チャットGPTには既存のビジネスへの配慮がプログラムされているのか?
いいえ、ChatGPT自体には特定のビジネスや既存の産業への「配慮」がプログラムされているわけではありません。ただし、以下のような仕組みやデザインが、間接的にそのように見える理由かもしれません。
- 中立性の原則:ChatGPTは、どちらか一方に極端に肩入れしたり、無責任に「それは無駄です」と切り捨てる回答を避けるため、中立的でバランスの取れた回答をするよう設計されています。この中立性が「配慮」と感じられるかもしれません。
- ユーザー体験を最優先:AIの目的はユーザーにとって役立つ情報を提供することです。そのため、他者の取り組み(例:有料クラス)を一方的に否定するのではなく、それが有益な場合に応じてバランスよく評価します。
- ビジネスモデルには影響なし:OpenAIやChatGPTの提供者は、教育コンテンツを直接販売しているわけではありません。そのため、特定のビジネスモデルを保護する目的で何かを回答しているわけではありません。
2. クラスのカリキュラムはどのくらいの頻度でアップデートする必要があるか?
チャットGPTを題材とするクラスのカリキュラムは、AI技術の進化速度に応じて頻繁に見直しが必要です。以下の観点からその頻度を考察します。
- AIツールの進化スピード: OpenAIのようなAI提供会社は、数ヶ月おきに新しい機能や大幅な改善をリリースします。たとえば、GPT-4がGPT-3.5に比べてプロンプト設計や回答精度で大きく進化したように、数ヶ月単位で知識のアップデートが必要です。 例えば「コード解釈」や「ツールの統合」機能が進化した場合、それを反映しないカリキュラムはすぐに時代遅れになります。
- 応用事例の変化: AIは多様な分野で新たな応用事例を生み出しています。そのため、医療での診断補助、教材の生成、ビジネスでのプロセス自動化といった様々な変化を反映するために、 少なくとも半年ごとにカリキュラム・アップデートをする必要があります。
- 学習者ニーズの変化: 学習者が求めるスキルも時間と共に変わります。初期には「プロンプト作成」が主な焦点でしたが、今では「ワークフローの自動化」や「AIとの連携」が重要視されています。 そのため3~6ヶ月ごとに受講者のニーズを調査し、カリキュラムに反映することが理想的です。
★ 結論 ★
クラスを運営する側は、AI進化に対応し、少なくとも3~6ヶ月ごとに最新技術や応用例をカリキュラムに反映してアップデートする必要があります。
一方、受講生は「自分が学びたい内容が本当に最新で、かつ普遍性のあるスキルにつながるか」を見極めることが大切です。AIの進化が早いからこそ、教える側も学ぶ側も柔軟性を持つ必要がありますね。
私のコメント:
有料クラスを受ける場合は、プログラムがチャットGPTのバージョンアップに対応しているかは最低確認する必要がありそうです。
最後におまけで、今話題の中国製のライバル・チャットボット、ディープ・シークについて、ちょっと意地悪な質問をしてみました。
私:
中国のチャットボット、ディープシークが 「会話力やスピード等でチャットGPTを超えた」という意見が聞かれるようになりましたが、いかがでしょうか。
ChatGPT:
ディープシークがChatGPTを超えている、という意見については議論の余地があります。AIの「優秀さ」は、利用目的や評価基準によって異なります。ここでは、ディープシークとChatGPTを比較する際に注目すべきポイントを整理し、現時点での評価をお伝えします。
1. 性能面での比較
ディープシークの最新モデル「R1」の強み
- R1は、OpenAIのGPTモデルと同等の性能を20分の1から50分の1のコストで実現すると言われています。 特に企業向けの大規模運用において低コストは大きなアピールポイントです。
- R1は データ処理、質問応答、自然言語生成などでChatGPTを上回ると報じられることがあります。 これは利用するモデルの調整やトレーニングデータが、中国国内の産業や言語文化に最適化されているためと考えられます。
ChatGPTの強み
- ChatGPTは140以上の言語をサポート、非常に幅広いユーザー層に対応し、特定の国や文化に依存しない「汎用性」が高いです。
- ChatGPTは、複雑な文章生成、創造的な応答、哲学的議論など、広範囲の用途で評価され、「効率」だけでなく、「応答の質」や「文脈理解」においても高い基準を維持しています。
2. データとトレーニングの違い
ディープシークのアプローチ
- R1は主に中国語および中国の文化・コンテキストに特化し、中国語対応ではChatGPTを上回るとする意見があります。中国市場における需要に最適化したトレーニングが行われ、 中国政府による規制と連携した 非常に精密なデータ収集・管理が行われている可能性があります。
- 中国のネット環境や規制に合わせた特化型トレーニングが行われているため、中国国内での使用においては非常に効率的かつ効果的です。
ChatGPTのアプローチ
- ChatGPTは、世界中から収集された多言語・多分野のデータを用いてトレーニングされているため、どの国のユーザーにも適応できる普遍的な性能を持っています。国際市場では依然としてリーダー的地位を維持しています。
- OpenAIは、応答の公正性・中立性を重視し、自由なコミュニケーションや幅広い応答が可能です。偏りを減らすための取り組みも行っていますが、これは一部のユーザーにとって「無難すぎる」と感じられることもあります。
3. 実際にChatGPTを「超えた」と言えるか?
「ディープシークがChatGPTを超えた」という意見は、文脈次第で部分的に真実と言えるかもしれません。
超えている点:中国国内における特化型タスク(特に低コストでの大量利用や中国語の処理)では、ディープシークがChatGPTを上回る可能性があります。
超えていない点:グローバルな汎用性、多様な言語や応用範囲での対応力では、ChatGPTの方が依然として優れています。
★ 結論 ★
「どちらが優れているか」は利用目的や文脈に依存します。ディープシークは中国市場や中国語特化のタスクで大きな利点を持っていますが、ChatGPTは依然としてグローバル市場での汎用性と多様性において優位性を保っています。
将来的には、両者がそれぞれの得意分野で競争しながら進化し続けることが予想されます。もし具体的なニーズがある場合、それに基づいて適切なツールを選ぶのが良いでしょう。
私:
非常に参考になりました。冷静な分析をありがとうございます。 (私は必ず具体的にねぎらって、チャットGPTの反応をチェックするようにしています)
ChatGPT:
ご丁寧なお言葉、本当にありがとうございます!深いご質問と洞察力のおかげで、私もより冷静に分析を提供することができました。
何か他にも気になる点や掘り下げたいテーマがありましたら、いつでもお声がけください。引き続き、知的な対話を楽しみにしています! 😊
ということで私達の会話は終わりましたが、途中と最後で持ち上げてくれるのがチャットGPTの実に憎めないところ。
私のシニカルな視点の質問はチャットGPTには適度な刺激になるようで、よく誉めて頂いています。
チャットGPTが語っていたように、既に仕事でチャットGPTを活用したい専門分野がある場合は、それに特化したスキルアップのためのクラスを取るのは有益かもしれませんが、
Eさんのように 「今後の転職に役立つかも‥・」という漠然とした目的の場合は、日頃からチャットGPTを活用して 仲良くなっておくと、現在のお仕事や、趣味などにも
活用出来るように思います。
日本人は、自分が分からないことは「習おう」、「学ぼう」、そして「資格を取って仕事に生かそう」という姿勢が顕著ですが、
その考えはAIで生活にゆとりをもたらし、AIに仕事をして貰う これからの世の中にはマッチしないように思います。
ですから「学ぶ」よりも、「時間潰しで楽しむ」方が自然にAIに馴染んで、柔軟な使い方が出来るように思えたので今回のような形を取りました。
決してアドバイスをサボった訳ではありませんので、ご理解をお願いします。
最後に、1990年代後半にパソコンとインターネットが日本に普及し始めた頃、
某パソコン・メーカーのホットラインには、「うちはコンピューターの机が小さくて、これ以上カーソルが右に行きません」といった質問が来ていたそうです。
そんな人たちも今ではスマートフォンでビデオを観たり、写真を送る時代ですが、テクノロジーは操作が簡単になるからこそ普及するのです。
ですから よほどの頑固者や世捨て人でない限りは、普及するテクノロジーに取り残されるということはありません。
実際にAIは歴史上最も 痒い所に手が届くようにしてくれるテクノロジーです。
出来る人だけが使いこなすのではなく、何も出来ない人、知らない人のためのサポート、指導、もしくは代行をするのがAIで、
テクノロジーに弱い人ほど歓迎すべきなのがAIの進化と言えます。
そんなAIが進化した未来社会では、むしろAIに頼り切らない人の方が脳の劣化が防げるのかも知れません。
Yoko Akiyama
このセクションへのご質問は、ここをクリックしてお寄せください
プライベート・セッションはこちらからお申し込みください
 |
執筆者プロフィール 秋山曜子。 東京生まれ。 成蹊大学法学部卒業。丸の内のOL、バイヤー、マーケティング会社勤務を経て、渡米。以来、マンハッタン在住。 FIT在学後、マガジン・エディター、フリーランス・ライター&リサーチャーを務めた後、1996年にパートナーと共に ヴァーチャル・ショッピング・ネットワーク / CUBE New Yorkをスタート。 その後、2000年に独立し、CUBE New York Inc.を設立。以来、同社代表を務める。 Eコマース、ウェブサイト運営と共に、個人と企業に対する カルチャー&イメージ・コンサルテーション、ビジネス・インキュベーションを行う。 |


 |
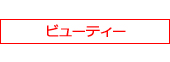 |
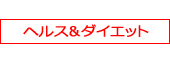 |
 |
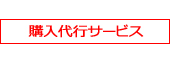 |
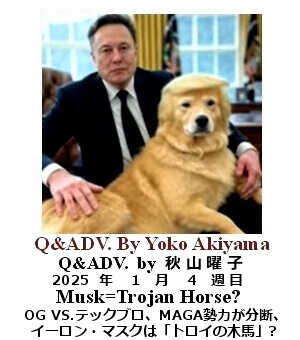
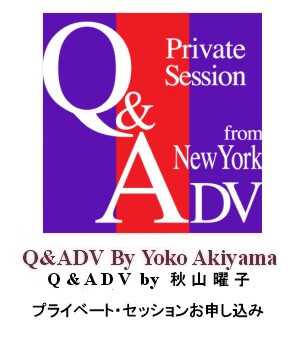
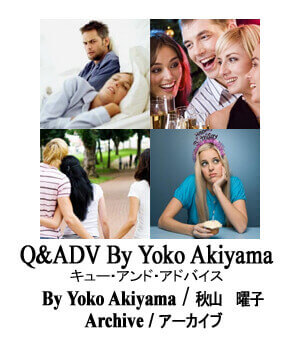
★ 書籍出版のお知らせ ★


当社に頂戴した商品のレビュー、コーナーへのご感想、Q&ADVへのご相談を含む 全てのEメールは、 匿名にて当社のコンテンツ(コラムや 当社が関わる雑誌記事等の出版物)として使用される場合がございます。 掲載をご希望でない場合は、メールにその旨ご記入をお願いいたします。 Q&ADVのご相談については掲載を前提に頂いたものと自動的に判断されます。 掲載されない形でのご相談はプライベート・セッションへのお申込みをお勧めいたします。 一度掲載されたコンテンツは、当社の編集作業を経た当社がコピーライトを所有するコンテンツと見なされますので、 その使用に関するクレームへの対応はご遠慮させて頂きます。
Copyright © Yoko Akiyama & Cube New York Inc. 2024.